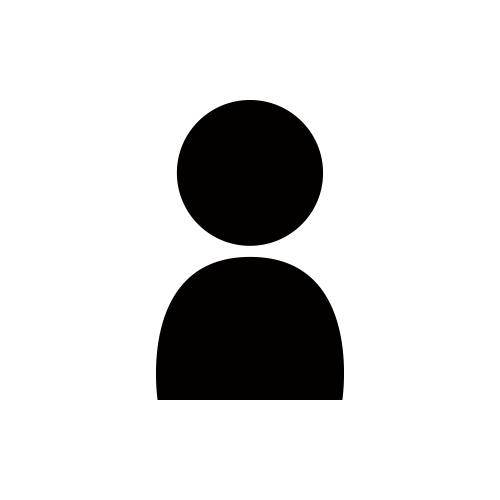ヘッドマウントディスプレイ(HMD)とは
ヘッドマウントディスプレイ(HMD)は、頭部に装着して使用する小型ディスプレイ装置であり、「VRゴーグル」や「ヘッドセット」とも呼ばれます。利用者の目の前を覆うようにディスプレイ(多くは左右の目用に2つ)を配置し、視界全体に映像を映し出すことで高い没入感を得られるのが特徴です。従来の据え置き型ディスプレイとは異なり、HMDは装着者の視線の向きに関わらず常に目の前に映像が表示されるため、首や体の動きに合わせて映像世界を見回すことができます。また、頭部の動きを検知するセンサー(ジャイロスコープや加速度計など)を内蔵し、動きに合わせて映像をリアルタイムに変化させることで、利用者はあたかも仮想空間の中に入り込んだような体験ができます。
図:2015年に開催されたMadrid Games WeekでVRヘッドセットを体験する来場者。HMDはゴーグル状の装置で視界を覆い、左右の目に別々の映像を投影することで立体視の3D映像を実現する。ヘッドフォンと併用すれば視覚と聴覚を仮想世界に集中させることができ、非常に高い没入感(イマーシブな体験)を生み出す。
HMDには大きく分けて非透過型(遮蔽型)と透過型の2種類があります。非透過型HMDは外界の光を完全に遮断し、装着者の視界を仮想映像のみとするタイプで、主にVR(バーチャルリアリティ)用途に使われます。一方、透過型HMDは周囲の現実世界を見ながら情報を重ねて表示できるタイプで、AR(拡張現実)用途の光学シースルー(透明なスクリーンに映像を投影)や、カメラ経由で現実映像を取り込むビデオシースルー方式があります。例えば、MicrosoftのHoloLensやMagic Leap Oneのように現実空間に3Dホログラムを重ねて表示するデバイスは透過型HMDの一種です。また、表示方式としてはハーフミラー等に映像を映し出す虚像投影型や、レーザーで網膜に直接像を結ぶ網膜投影型などの技術も研究されています。映像表現においては片眼用の単眼HMDと両眼用の双眼HMDがあり、両眼HMDでは左右でわずかに異なる映像を表示することで人間の両眼視差を利用した立体視(ステレオ3D映像)が可能です。
HMDには装着者の動きをどこまでトラッキングできるかによって**3自由度(3DoF)と6自由度(6DoF)**の区別もあります。3DoFのHMDは上下・左右・前後の回転(首振り)だけを検出でき、視点の位置移動までは反映できませんが、360度動画の視聴など基本的なVR体験には利用できます。6DoF対応のHMDではさらに前後・左右・上下方向の位置移動も検出でき、仮想空間内を歩き回ったり物体に近づいたりといったインタラクションが可能になります。ただし6DoF実現には高度なセンサーやカメラを用いた位置追跡システムが必要で、以前は高価で大型になりがちでした。しかし近年では内蔵カメラで自己位置を把握するインサイドアウト方式により、外部センサー不要で6DoFを実現するスタンドアロン型HMD(後述するMeta社のQuestシリーズなど)も登場しています。
歴史
HMDの概念は非常に古く、原型となる発明は1960年代にまで遡ります。1950年代後半~60年代初頭には、映画技術者のモートン・ヘイリグが没入型映像装置「Sensorama(センソラマ)」を開発し、1960年には世界で初めてのHMDとなる「テレスフィア・マスク」の特許を取得しましたbtw.media。テレスフィア・マスクは簡易なヘッドセット型の装置で、装着者に視差のある立体映像とステレオ音声を提供するものでしたが、外界とのインタラクションや位置トラッキング機能はなく、いわば「個人向け3Dテレビ」のようなものでしたbtw.media。
その数年後、1968年にはコンピュータ技術者のアイバン・サザランドとその学生ボブ・スプロールが、コンピュータに接続して動作する初のヘッドマウント型ディスプレイ装置「ダモクレスの剣(The Sword of Damocles)」を発表しましたvrs.org.uk。ダモクレスの剣は天井から吊り下げて使用するほど大型で重い装置でしたが、装着者の頭部の向きをセンサーで検知し、それに合わせて簡単なワイヤーフレームのCG映像を左右別々のスクリーンに表示するという、現在のVR HMDの原型となるシステムでしたvrs.org.uk。この装置によって「コンピュータが生成する仮想の部屋」を見渡す体験が初めて実現し、今日のVR技術の黎明となりました。当時サザランドは自身の論文で「究極のディスプレイ(The Ultimate Display)」構想を語り、コンピュータによって現実と見分けがつかない仮想世界を作り出す未来像を示唆していますvrs.org.ukvrs.org.uk。
その後も軍事分野などでHMD技術の研究は細々と続きますが、本格的にバーチャルリアリティ (VR) という概念が注目を集め出すのは1980年代後半になってからです。1985年にはアメリカでVPLリサーチ社が設立され、創業者のジャロン・ラニアーらによって、手の動きを検知する「データグローブ」や頭部装着型の映像装置「アイフォン (EyePhone)」といった先進的なVRデバイスが次々と開発・商品化されましたvrs.org.uk。ラニアーは1987年に「バーチャルリアリティ(仮想現実)」という用語を提唱した人物として知られ、VPL社は世界で初めて商用のVR用HMD(アイフォン)やデータグローブを販売した企業でもありますvrs.org.uk。当時のアイフォンは1台9,400ドル、データグローブは1セット9,000ドルという非常に高価なものでしたが、研究者や一部企業に提供され、VR技術への期待が高まり始めました。
1990年代前半にはVRブームの第一次波が到来し、一般向けの製品や体験施設も登場しました。英国のVirtuality社が開発したアーケード用VRゲームマシン(ゴーグル型HMDと体感コントローラを組み合わせたシステム)は世界各地のゲームセンターに設置されましたし、セガは家庭用ゲーム機向けに「セガVR」というHMDを1993年に発表しました(価格200ドル程度を想定)vrs.org.uk。任天堂も1995年に据え置き型の3Dゲーム機「バーチャルボーイ」を発売し、裸眼立体視こそできないもののヘッドセットを覗き込む形で簡易的なVRゲーム体験を提供しましたvrs.org.uk。しかしこの頃のHMDやVRシステムは高価であり、映像も荒く視野角も狭いなど技術的制約が大きく、十分な満足感を得るには程遠いものでした。セガVRは技術的困難から発売中止となり、バーチャルボーイも表示が単色(赤黒2色)であることや長時間の使用で目や首が疲れることなどが嫌われ、商業的に失敗していますvrs.org.uk。また当時のVR体験では描画遅延やトラッキング精度の低さからくる3D酔い(VR酔い)も問題となり、多くのユーザーが長時間の利用に耐えられない状況でした。この結果、90年代のVRブームは一時の盛り上がりの後に急速にしぼんでしまい、VR/HMD技術はしばらく「冬の時代」を迎えることになります。
転機が訪れたのはそれから約20年後、2010年代前半のことです。低価格・高性能な加速度センサーやディスプレイを備えたスマートフォンが普及したことで、小型ディスプレイやセンサー類のコストが大幅に下がり、個人向けの高性能HMDを実現できる土壌が整いました。2012年には若き技術者パルマー・ラッキーが開発した試作HMD「Oculus Rift」がクラウドファンディングサイトKickstarterで資金調達に成功し、大きな話題を呼びますmagazine-k.jp。これをきっかけにVR業界への機運が一気に高まり、Oculus社は2014年にFacebook(現Meta社)によって20億ドルで買収されましたmagazine-k.jp。Facebookのマーク・ザッカーバーグCEOが「VRを将来10億人規模に普及させる」と宣言したこともあり、各国の大手企業がこぞってVR市場に参入しますmagazine-k.jp。サムスンはスマホを装着して使うGear VRを発売し、ソニーは家庭用ゲーム機向けのPlayStation VRを開発、HTCはValve社と提携してPC向け高性能HMDHTC Viveをリリースするなど、2016年頃には主要メーカーのVRデバイスが出揃いましたmagazine-k.jp。日本でも2016年は「VR元年」と呼ばれ、VR関連のニュースが連日メディアを賑わせましたmagazine-k.jp。この年、世界のVR市場規模は約270億ドルに達し、以降もしばらく年率70%前後の成長が見込まれるといった予測も出されていますmagazine-k.jp。
用途・応用分野
HMDはその没入型の表示能力を活かし、エンターテインメントから産業応用まで幅広い分野で利用されています。最も一般的な用途はVRゲームを中心としたエンタメ分野です。HMDと頭部トラッキング技術を組み合わせることで、ユーザーの顔の向きに合わせて360度見渡せる仮想現実空間が実現できるため、これまでにない臨場感のゲーム体験が可能になります。家庭用のVRゲーム機(例:PlayStation VR、Meta Questシリーズ)やPC接続型のVRシステム(Valve Indexなど)により、ユーザーは自宅にいながらバーチャル空間でのゲームや冒険を楽しめます。
映像視聴分野でもHMDは活用されています。映画や動画をHMDで視聴すると、まるで目前に大スクリーンがあるかのような迫力ある映像体験が得られるため、プライベートシアター的な用途でHMDを利用する人もいます。ただし長時間の映画視聴では字幕を見る際の目の動きが負担になる、副作用として酔いやすい等の課題も指摘されています。
軍事・訓練分野では、HMDはパイロット用ディスプレイやシミュレーターとして古くから利用されてきました。戦闘機のパイロット向けには従来コクピット内にヘッドアップディスプレイ(HUD)が使われてきましたが、近年ではHUDの情報をヘルメットのバイザーに投影するヘルメットマウントディスプレイが実用化されています。例えばアメリカ軍のF-35戦闘機ではパイロットのヘルメットに内蔵されたHMDに各種情報が映し出され、周囲を見回すだけでターゲットを捉えたり計器を確認できるようになっています。しかしヘルメット内蔵型の機器は重量増による負担が問題となりやすく、カーボン素材の活用などで軽量化が図られています。それ以外にも、訓練シミュレーター用途としてHMDは古くから用いられており、屋内でのパラシュート降下訓練、射撃訓練などにVRを活用する例があります。現実では危険を伴う訓練も、VR空間であれば安全に繰り返し実践できるメリットがあります。
産業・業務支援の領域でもHMDの応用が進んでいます。例えば建築・土木設計において完成予定建造物の内部をVRで歩き回って検証したり、自動車のデザイン検討にVRを使って実物大モデルを確認するといった利用があります。また作業現場で透過型HMD(いわゆるスマートグラス)を装着し、視界にマニュアルやチェックリストを投影して作業効率を上げるといったAR支援も実用化されています。近年注目された例としては、中国で警察官が顔認証機能付きのスマートグラス型HMDを導入し、犯罪者や行方不明者の顔をリアルタイムで照合するといった用途も報じられましたdcross.impress.co.jpdcross.impress.co.jp。さらに、新型コロナウイルス感染拡大時には中国で体温スクリーニングにHMDを活用したスマートヘルメットが警備当局に使われた例もありますdcross.impress.co.jp。
スポーツ分野でもVR/AR技術とHMDの組み合わせが活躍し始めています。プロスポーツのトレーニングにVRシミュレーションを導入する例が増えており、選手や審判がHMDを装着して実際の試合さながらの状況を仮想空間で経験することで、効率的にスキルを磨く試みが行われていますgroup.ntt。例えば野球では、打者がVR上で様々な投手の投球を繰り返し体験できるバッティング練習システムが登場しており、実際にソフトバンクホークスなどプロ野球チームが導入していますgroup.ntt。また、AR技術を使った新しいスポーツ競技も生まれており、HMDとセンサーを装着してエナジーボールを投げ合う「HADO」のような対戦型ARスポーツも人気を博しています。
医学・医療の領域もHMD活用の有望な分野です。手術支援ロボットと組み合わせ、執刀医がHMD越しに術野の拡大映像やガイドラインを確認しながら手術を行うシステムの研究が進められています。また研修医や医学生の手術トレーニングにVRを用いることで、現実の患者を使わずに繰り返し手技を練習できるようになります。実際に、HMDとVR技術で熟練医の手術手技を仮想再現し、新人医師が追体験できる「手術手技追従トレーニング」システムが開発され、その教育効果が検証されていますjstage.jst.go.jp。リハビリテーション分野でも、HMDを装着してバーチャル空間内で身体を動かすリハビリ訓練や、痛みの軽減・恐怖症の克服といったVR療法への応用が報告されています。
このようにHMDは人間の視覚・空間知覚に訴えるデバイスであるため、その応用範囲は多岐にわたります。今後もコンテンツやソフトウェアの工夫次第で、新たな産業分野での活用が開拓されていくでしょう。
技術的進歩と現状
HMDを取り巻くハードウェア技術は近年飛躍的に向上し、現在市販されている製品は高解像度ディスプレイや広視野角レンズ、高精度なヘッドトラッキングを備えています。2016年の「VR元年」以降登場した代表的なVR HMDとして、Oculus(現Meta)の「Rift」シリーズ、HTCとValveの「Vive」シリーズ、ソニーの「PlayStation VR」シリーズなどが挙げられますmagazine-k.jp。これらはいずれも両眼で100度以上の視野角を持つ高精細ディスプレイを搭載し、頭の動きを正確に検知することでスムーズな360度視界を実現しましたmagazine-k.jp。特にソニーのPS VRは家庭用ゲーム機向けとして普及し、2016年の発売以降2020年までに累計500万台以上を販売しています。2019年には初の本格的スタンドアロン型VRヘッドセット「Oculus Quest」が発売され、PCやゲーム機なしで単体動作する手軽さと6DoF対応の本格VR体験を両立させたことで市場をさらに拡大しましたmagazine-k.jp。
現在(2020年代半ば)のVR/HMD市場を牽引するのは、Meta社の「Quest」シリーズです。初代Questおよび改良版のQuest 2は全世界でヒットし、累計販売台数はすでに2000万台を超えたと報じられていますdcross.impress.co.jp。これにより、Meta社(旧Oculus)がHMD市場シェアのトップに立っていますdcross.impress.co.jp。ソニーも最新機種「PlayStation VR2」を2023年に発売し、ゲーム分野で引き続き重要なプレイヤーです。他にはPC向け高級機としてValve社のIndexや、業務用途向けに高解像度・高視野角を追求したVarjo社のHMDなど、用途に応じた多様な製品が市場に出揃っています。
一方、AR分野では2016年のMicrosoft HoloLens発売以降、産業用途を中心に透過型HMD(スマートグラス)の活用が進んでいます。例えばエンジニアがHoloLensをかけて機器の整備を行う際、視界にマニュアルや組立手順を表示するといったソリューションが各所で試験導入されています。またMagic Leap社のデバイスなども一時注目を集めました。MR(複合現実)と呼ばれる、現実世界と仮想物体をシームレスに融合する技術も登場しており、HMDが現実と仮想の両方を映し出すプラットフォームとして発展しつつあります。
2023年にはApple社が満を持して独自の高性能HMD「Vision Pro」を発表しました。Vision Proは周囲の現実世界にデジタルコンテンツを重ね合わせる空間コンピューティングというコンセプトを掲げたデバイスで、極めて高解像度のディスプレイや先進的なハンドトラッキング機能を備えていますdcross.impress.co.jp。価格も従来製品より大幅に高い設定ですが、新たなコンピューティングプラットフォームとして注目されており、VR/AR業界に刺激を与えていますdcross.impress.co.jp。
市場の規模としては、2023年の世界AR/VRヘッドセット出荷台数は約1000万台前後と推定されており、前年比でやや成長が鈍化したものの依然として堅調な需要があります(調査会社IDCによる)dcross.impress.co.jp。特に2020年頃からのコロナ禍でリモート需要が高まったこともあり、一時的に企業の研修やバーチャル会議用途でHMD導入が進む動きも見られました。日本国内でも2021年にKDDIなどがVR会議サービスを開始するなど、ビジネス分野での活用例が増えています。
現状のHMDに関する技術的課題としては、「さらなる小型・軽量化」と「長時間使用に耐える快適性」が挙げられますdcross.impress.co.jp。ヘッドセットが重いと首への負担が大きく、バッテリー駆動時間の短さもモバイル利用を制限します。メーカー各社は光学系に薄型のパンケーキレンズを採用したり、マイクロOLEDディスプレイで部品サイズを縮小したりといった工夫で、ゴーグル部分の薄型軽量化を進めています。また、視差調整やピント調節の技術改良により、VR酔いの軽減や視界の解像度向上も図られています。次世代機では目玉の動きを追跡するアイトラッキングや表情を捉えるセンサーなども搭載され始めており、アバター(仮想分身)に本人の視線や表情を反映させることで、より人間らしいコミュニケーションを取れるようにする試みもあります。
販売台数と市場動向
前述のように、Meta社のQuestシリーズが累計2000万台以上と突出した販売実績を持っていますが、それ以外の主要HMDも一定の普及が進んでいます。初代Oculus RiftやHTC Viveは正確な販売数は公表されていませんが、いずれも数十万台規模を売り上げVRゲーマー層に浸透しました。ソニーのPlayStation VR(初代)は比較的安価かつPS4に接続する手軽さから500万台以上を販売し、コンシューマー向けVRデバイスとして成功を収めました。2023年2月に発売された後継機のPS VR2は対応タイトルの拡充とPS5の普及次第ですが、高精細な映像表現とアイトラッキング機能を備え今後の販売が期待されています。
世界全体のVR/ARヘッドセット市場を見ると、2022年頃までは年成長率が50%を超える急拡大期でしたが、直近では成長ペースがやや緩やかになりつつあります。ある調査によれば2023年の世界出荷台数は約745万台と前年から18%ほど減少したものの、2024年以降はApple参入なども相まって再び需要が伸び、2025年には出荷台数が急回復するとの予測もありますbunsekik.com。一方でIDCの分析では2023年にHMD市場が前年比30%増の成長を示し、その中でMeta(Oculus/Quest)のシェアが拡大しているとも報じられており、市場予測には見解の分かれる部分もありますdcross.impress.co.jp。いずれにせよ数年内には年間出荷台数が数千万台規模に達するとの見方が多く、HMD市場はニッチなホビー製品から大衆向けデバイスへと着実に歩みを進めています。
地域別では北米・アジアが中心ですが、日本国内でも2023年のHMD出荷台数は推定50万台近くに達したとの調査がありますyanoict.com。これはコロナ禍によるDX(デジタルトランスフォーメーション)の流れや、メタバース・ブームによる法人需要が少なからず貢献していると考えられます。実際、Facebook改めMeta社が提唱するメタバース構想に多くの企業が刺激を受け、バーチャルイベントやVR会議のためにHMDを導入するケースが増えました。また、教育現場でVR教材を導入する学校や、観光PRにVR映像を活用する自治体など、新たな需要も生まれています。
消費者市場においては、若年層のHMD受容度が高まっている点にも注目すべきです。2024年に米国で実施された調査では、Z世代(10~20代)の30%以上が既に何らかのVR機器を所有しているとの結果が出ていますdcross.impress.co.jp。安価なスマホ用簡易VRグラスから高級機まで含めた数字とはいえ、デジタルネイティブ世代にとってVRは珍しいものではなくなりつつある証拠と言えるでしょう。
これからの展望
HMD技術の今後の展望としては、まずデバイスそのものの進化が挙げられます。さらなる軽量化・薄型化・高解像度化は当然として、将来的にはメガネに近いフォームファクタでAR/VRを両立できるシームレスなXRデバイスの実現が目標となっています。現在はVR用とAR用でデバイスが分かれている状況ですが、光学技術のブレークスルーによって一つのアイウェアで現実世界への情報投影と没入型VRの双方を切り替えられるようになる可能性があります。そのための要素技術として、可変フォーカスレンズや網膜投影、指向性スピーカー、超小型カメラやマイクによるセンシング強化などが研究されています。
コンテンツ面では、メタバースや仮想空間サービスの発展がHMD普及の鍵を握るでしょう。現在のところVRのキラーコンテンツはゲーム分野に限られていますが、将来的に仕事や社交、買い物など日常的な活動を仮想空間上で行うようになれば、HMDは“次のスマートフォン”とも言える地位を得るかもしれません。Meta社(旧Facebook)は「将来、人々がメタバース上で交流する時代が来る」として巨額の投資を続けていますが、その実現には使いやすく快適なHMDデバイスの存在が不可欠です。dcross.impress.co.jp今後、よりリアルなアバター同士で会話したり共同作業したりできるプラットフォームが整い、さらにそこに生成AI(人工知能)の技術が組み合わされることで、HMDを介した仮想世界体験が次なるイノベーションとなる可能性があります。
とはいえ課題も残ります。HMDの長時間使用による眼精疲労・酔い問題は完全には解決しておらず、誰もが日常的に装着するにはもう一段の技術進歩が必要です。また、高品質なHMDほど価格が高額になる傾向があるため、大衆向けに手頃な価格で行き渡るまでには時間がかかるでしょう。しかしスマートフォンがかつてそうであったように、技術の成熟と量産効果でコストが下がれば、HMDもいずれ一人一台の時代が来るかもしれません。
業界では今後数年間でXR市場がさらに拡大すると予測されています。ある試算では、2030年までにグローバルのメタバース関連市場規模が5000億ドルを超えるとも言われdcross.impress.co.jp、それを支えるデバイスとしてHMD/スマートグラスへの期待は大きいです。企業の調査でも、今後投資を増やす技術分野として「メタバース/XR」を挙げる経営者が少なくないという結果が出ていますdcross.impress.co.jp。こうした追い風の中、AppleやMetaだけでなく、多くのテック企業やスタートアップが次世代HMD開発にしのぎを削っています。
まとめると、ヘッドマウントディスプレイは約60年の年月を経て黎明期の研究装置から身近なデジタルガジェットへと変貌を遂げました。歴史的には紆余曲折がありましたが、現在では現実と仮想を結ぶインタフェースの中心的存在として期待されています。今後も技術の進歩とともにHMDは進化を続け、私たちの仕事や生活、娯楽のスタイルを変えていく可能性があります。その未来像としては、「日常的に着けるスマートグラスで現実世界にデジタル情報が当たり前に重ね合わされる」「遠く離れた人同士がHMD越しにまるで同じ空間にいるかのように交流できる」――かつてSFで描かれたような世界が現実になる日も、そう遠くないのかもしれません。
参考文献・情報源:ヘッドマウントディスプレイの歴史と現状に関する各種記事・レポートbtw.mediavrs.org.ukvrs.org.ukvrs.org.ukmagazine-k.jpdcross.impress.co.jpdcross.impress.co.jpgroup.nttjstage.jst.go.jpdcross.impress.co.jpなど。